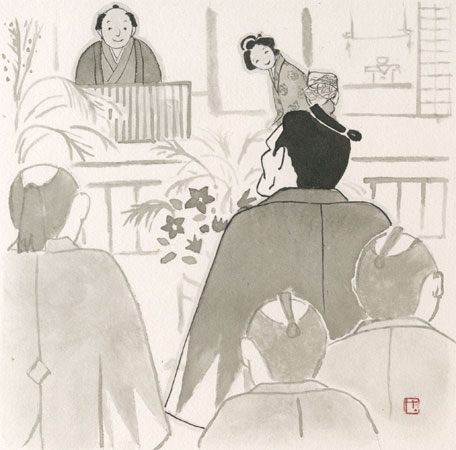
道具を知るとお茶はもっと楽しい!「とびきり屋見立て帖」
*アイキャッチ画像は「オール讀物」掲載時の挿絵をお借りしました(北村さゆりさん画)。
毎日暑い日が続きますね。
先日やっと和室の窓の外に簾をつけて、見た目にも涼しくなりました!
猫も興味津々のようで、エアコンの効いた部屋には来ずに、和室の窓際からじっと外を見ています^^
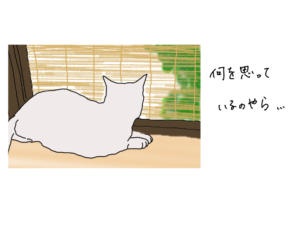 さて最近、お茶の先輩に勧められた本を読んで見たら、ことのほか面白くてはまってしまいました。
さて最近、お茶の先輩に勧められた本を読んで見たら、ことのほか面白くてはまってしまいました。
お茶好きの方、京都好きの方、茶道具好きの方、幕末好きの方には特におすすめなので、ご紹介したいと思います。
舞台は京都、江戸末期の動乱のさなか。
主人公は道具屋「とびきり屋」の若夫婦、真之介とゆず。
真之介は独立前に老舗の茶道具屋で修行しており、その道具屋の娘であるゆずと出会います。
2人は小さい頃から本物の道具を見て触って育ったこともあり、若いながらかなりの道具好きでかなりの目利き。
その目利きを頼りに、店の者達とともに難関を乗り越えていく、痛快短編小説です。
「とびきり屋」には茶の湯の家元だけでなく、あの新撰組や桂小五郎、坂本龍馬など幕末の有名人もたくさん出入りします。
京都の町の様子や当時の人々の暮らしなどがリアルに描かれていて、実際に当時の三条通りにこんな道具屋があったのでは、と思ってしまうほど。
そしてなんといっても、筆者である山本兼一さんの茶道具の描写が秀逸です!
道具そのものの書き方はもちろん、真之介とゆずが道具の見せ方売り方を工夫するところなどは読んでいて面白く、例えば、以前売ってしまった鉢が後に手元に戻ってきた時には、売った時にはなかった塗り蓋が付いて茶道具になっていたり。
ある時は仕入れた茶器を入れる仕覆をゆずが縫ったり。
こうやってまわりまわって、現代のお道具があるんだなあと思うとなんだか不思議というか、感じるものがあります。
山本兼一さんといえば、「利休にたずねよ」の著者。
ご本人も京都出身で表千家のお茶を習っておられ、お道具屋さんとの付き合いもあったそうで、「とびきり屋」の若夫婦のように、いい道具をたくさん見てこられたんだなあ、お道具が好きなんだろうなあというのが感じられます。
作中で素晴らしい茶道具を手にした夫婦の感動や興奮が、文章を通してこちらにも真っすぐに伝わってきます。
道具のうんちくもそうですが、真之介やゆずが語る商いの極意や心得なども、なるほどとうなづける言葉が多く出てきます。
2人の仲の良さと素直さが周りの人たちにどう影響を与えるのか、「とびきり屋」を取り巻く人たちや道具達の移り変わりなど、続きが気になってしまい、4冊一気に読んでしまいました。
山本兼一さんは、惜しむらく2014年に亡くなっています。
故に「とびきり屋見立て帖シリーズ」も、図らずも4部完結となってしまいました。
続きが本当に楽しみだった作品なので、残念です。
三条大橋の目と鼻の先にあった「とびきり屋」。
暑さを忘れて引き込まれる作品です。
ぜひ読んでみてください。










